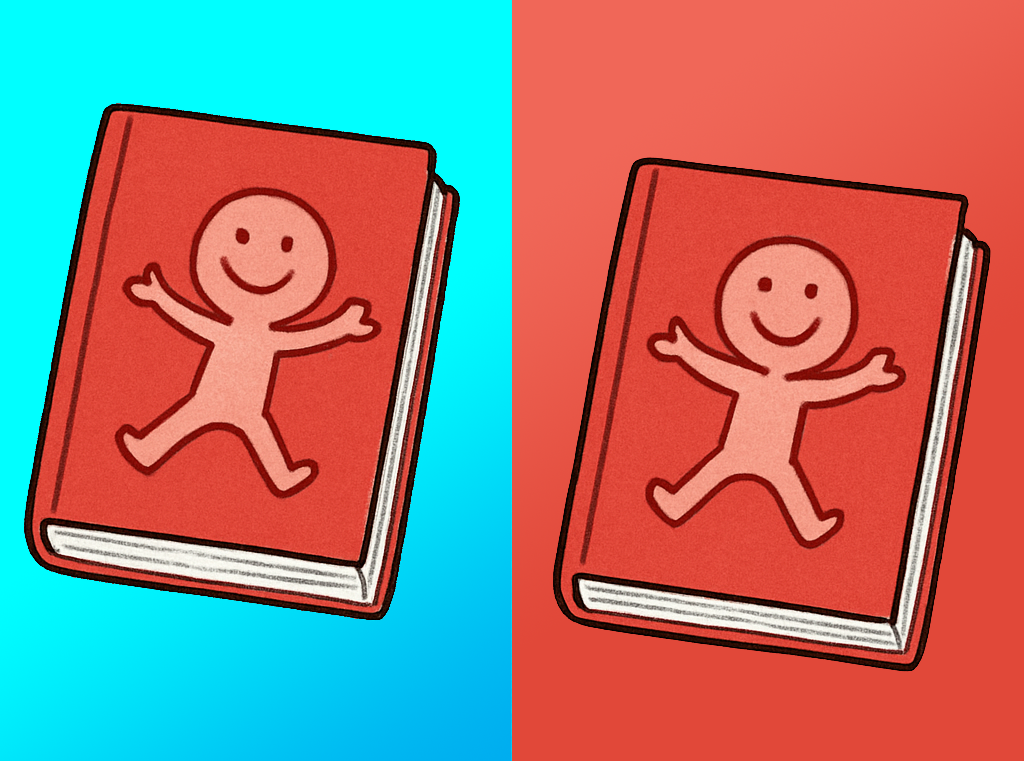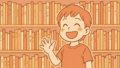「🐣練習編」では、楽に呼吸し発声するための身体認識についてお話ししました。
でも最終的には、それらの身体制御を意識しなくなる、いわゆる「自動化」することが大切です。
🎤 楽に呼吸し適切に発声することは、あくまでスタートライン。
意識は「声を出す自分自身」ではなく、
伝える「内容」と「相手」に向けられるべきです。
🗣️ 単純に滑舌がよく、リズムが整い、音圧が安定していればOK?
…それだけなら、読み上げソフトで十分という話になってしまいますよね。
👧 子どもに伝えるということ
では、絵本の読み聞かせにおいては、
「何を」「誰に」伝えていくのでしょうか?
👨👧 娘や児童館の子供たちに読み聞かせをし、共に遊ぶ中で感じたのは…
子どもたちは、歴史や用語・対処パターンを知らないから未熟に見えるだけで
目の前の出来事に対する感受性は、大人以上に鋭いということです。
📚 「子どもだからこの本でいいや」
というような見下した選び方や態度は、確実に見抜かれます。
私の娘は小学生の頃、某大学の児童文化研究会のボランティア活動を
「子どもをなめてるね」と、バッサリ切り捨てていました。
🧡 教えない・押しつけない
📌 子どもたちは、十分に大変な環境に生きています。
だからこそ、絵本でまで説教や教訓を押しつけず、
理屈抜きで楽しませたい、面白がらせたい。
これは、大人が芸能という「非日常」に癒しを求めるのと同じです。
子どもだって、心から癒されたいのです。
💬 実際、児童館の子どもたちと話していると
ネットから溢れる情報に晒され、強いストレスの中にいるのが伝わってきます。
(例えば「日本が今にも外国から攻撃される」と思っている子も…)
🕊️ そんな中で、絵本の時間は「ただの娯楽」ではありません。
心をほぐす、かけがえのない時間なのです。
👀 「語り手」としての覚悟
📌 この貴重な時間を、語り手の未熟さや押しつけで台無しにしたくはありません。
📌 現実問題として、現代の社会背景や語り手自身に付いている色を、完全に絵本の世界の後ろに隠すことは不可能です。
子どもたちは、
「この時にこういう場所でこういう男がこういう話をした」
という全体を受け取ります。
そのことを覚悟して絵本を選び、
読み聞かせをすることが大事だと思います。
🎙️私自身に関して言えば、子どもたちが初老のいかつい顔の男(=私)が熱心に楽しそうに読み語る姿を見て、その面白い話から、そしてそういう語り手の姿勢自体から、なにかをじんわり感じてくれたら嬉しいなと思っています。
📖 絵本の選び方について
そんな視点から、私は足かけ20年、絵本を選び続けてきました。
その中から、「読んで良かった!」と思えた作品を、このあとご紹介していきます。
📌 繰り返しになりますが、絵本は読む人や読む時代によって伝わるものが変わります。
その全体をよく考えて、じっくり選んでみてください。
➡️ 「2. 子供も大人も楽しい!絵本リスト」へ続きます。
🐣 練習編へ 🎤 仕事編へ(今後作成予定)